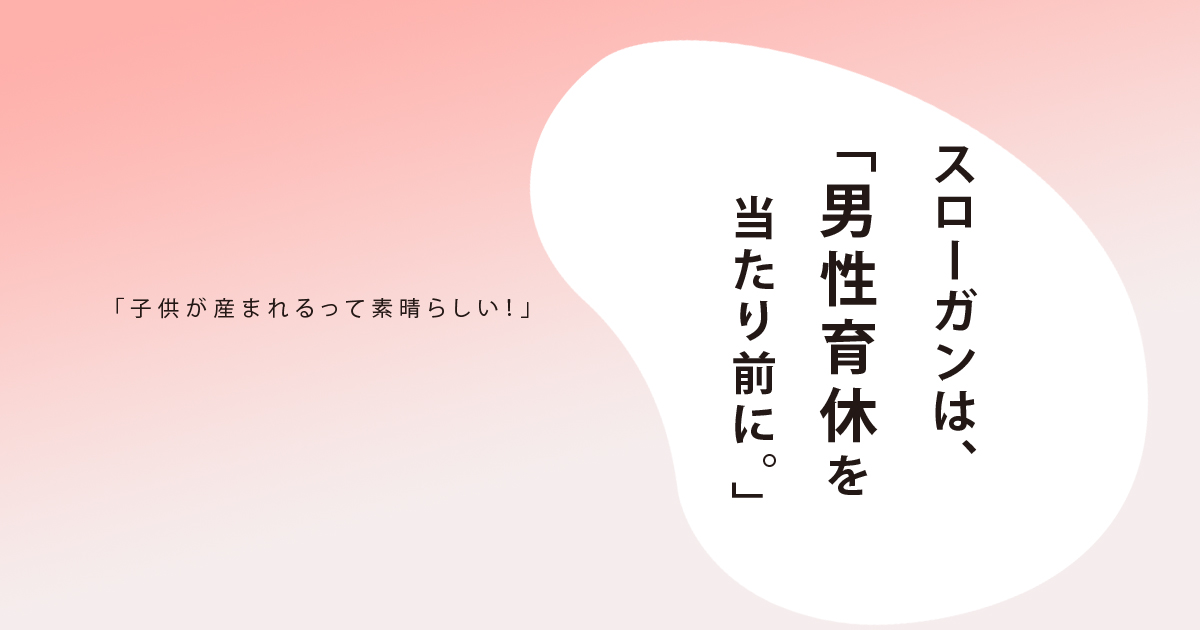厚生労働省の調査によれば、男性の育児休業取得率は令和5年度でついに30.1%を達成。令和6年度は更に数値を更新することと思われます。数年前には10%に満たないような状況だったのが、ここ数年で爆上がりした印象ですね。
令和7年4月からは、育児介護休業法の改正、出生後休業支援給付金の創設など、出産・育児関係の改正施行が予定されています。
昨年12月には両立支援助成金も拡充が行われたところですが、そもそもなぜ男性育休がこれほど推奨されているのしょうか。
男性育休を取得する意味とは
理由はやはり少子化対策。共働き世帯が増えた現代において、女性一人が出産・育児を担うのではなく、パートナーである男性にも関わりを持ってもらうことで、第二子以降の出生率アップに繋げていこうということです。
そして戦後、核家族化が進み、産後の不安定なホルモンバランスで孤独な育児を強いられる産婦のメンタルケアのために、一番近くにいる家族が寄り添う大切さも問われています。
私自身、第一子の子育ては全てが未知の世界であるにも関わらず、その孤独な試練に精神を病んだものです。
できれば男性の皆様には、育休を取るという事実だけに注目するのではなく、その中身が趣旨に沿ったものとなるよう、自分に何ができるのか考える機会を設けてもらいたいと思いますし、お住まいの地域や産院で開催している両親学級の受講も良いですね。生まれてくる子供はもちろん、何より愛するパートナーの女性のために!
育休は企業の戦略投資と考えるべし
しかし企業としては、従業員に「育休取ります」と言われてしまったら、業務の見直しや代替要員の検討など、さまざまな労力を割くことになるのは間違いない。社内結婚した夫婦がいたりすると、育休での欠員は2倍…。
とはいえ人手不足が顕著化し、思うような人材採用が叶わないご時世で、男性育休が取得できない企業は選ばれなくなる恐れがあるのも事実です。
育休取得意向の申し出があった際にはネガティブに捉えず、在籍従業員のスキルアップや生産性向上の機会だと考え、ぜひ積極的に企業の育休取得実績に繋げていただきたいと思います。
助成金も活用できる
雇用環境均等室の取り扱いとなっている「両立支援助成金」では、男性に限らず、従業員の育休取得に活用できるコースがいくつか用意されています。
この助成金の利用には、就業規則の整備と、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定が必要になるので、初めてチャレンジする事業主様で、どちらも準備していないという場合は少し大変かもしれません。
助成額もそこまで高額ではないのですが、育休取得意向の従業員がいた場合には前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、従業員の育休取得に前向きな事業主様を全力で応援します。
助成金活用、育休取得促進の社内研修など、お気軽にお問い合わせください。